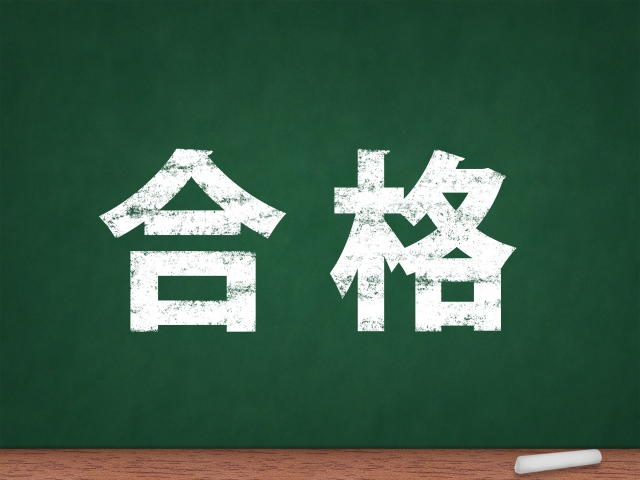文書問題より政治的な公平性を実現しているか否かだ

立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した〝総務省の内部文書〟という文書が注目されている。文書が作成された当時の総務相だった高市経済安全保障担当相が、文書にある自らの発言を「捏造」と真っ向から否定し、捏造でなかったら辞任すると主張したことで、「第二の永田メール事件では」などの見方も出た。
今回問題となった「政治的公平性」については放送法第4条で規定している。その「政治的公平性」についての解釈は、それまで放送事業者の番組全体を見て判断すると解釈されてきたが、安倍政権時代2016年2月に「一つ一つの番組を見て、全体を判断する」との見解が示された。小西議員は、この解釈変更に安倍元首相らの意向が強く働いたとしているわけだ。
この問題の行方や文書の真偽は措くとして、今問われるべきは、現在の民放テレビが、放送法が求めるような政治的公平性を保っているかということだろう。
実は、放送法4条では、放送局に4つを求めている。4条第1項では「公安及び善良な風俗を害しないこと」、2項では「政治的に公平であること」、3項が「報道は事実をまげないですること」、4項が「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」だ。
実際の民放テレビをみれば、こうした要請が順守されていないことは明らかだ。民放テレビの情報番組、ワイドショーと呼ばれるような番組では、コメンテーターと称する芸能人や有識者とされる人物が、一方的な意見を呈しているし、台本を見ながら意見を述べるようなケースもある。
そのコメントは常に一方的であり、放送法が求める「多くの角度から論点を明らかにする」ようなことは皆無と言ってもいいだろう。
新型コロナウイルス感染症が拡大した際には、政府は雇用調整助成金や、持続化給付金などさまざまな補助金や助成金を用意し、国民の生活を支えたが、テレビでは客が訪れなくなった飲食店を取り上げても、実際にどのような補助金、給付金など支給をどの程度受け、実際の経営状況や生活がどうなっているのかを報じたことはほとんどなく、政府の無策を批判するのが常だった。
これはほんの一例に過ぎないが、現在の民放テレビが「政治的に公平であること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を担保しているとは言い難いのは事実だ。