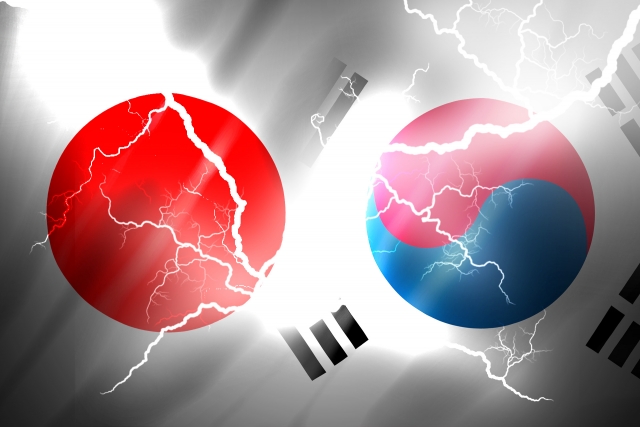立憲民主の野田代表。かつて「消費税は社会保障を支える責任ある財源」、今や「食品の消費税ゼロを」という変節
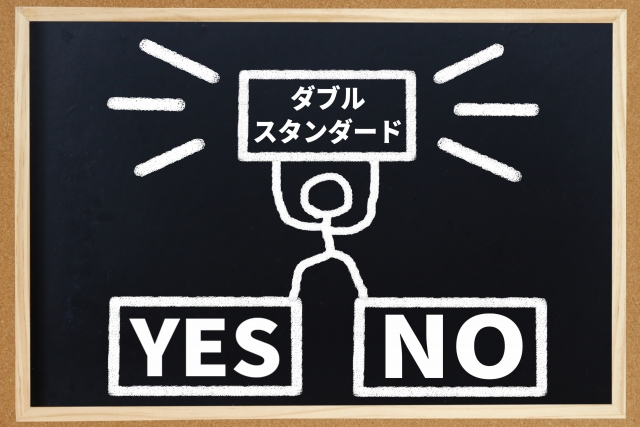
食料品の消費税ゼロを参院選の公約に掲げた立憲民主党。その代表は13年前の民主党政権時に首相として「消費税は社会保障を支える責任ある財源」と訴えた野田佳彦氏その人だ。かつて「貴重な財源」と言った野田氏が今では「消費税減税」。これは野田氏の〝変節〟だけではなく、かつて民主党だった議員も多く、政権を目指すという立憲民主党の政党として致命的失態と言えるのではないか。
2012年当時、野田首相は「次の世代に責任を果たすための不可避の改革」として「社会保障と税の一体改革」を掲げ、消費税率の8%から10%への段階的引き上げを主導した。選挙への逆風を覚悟のうえで法案成立にこぎつけた姿勢は、「筋を通す政治家」として一定の評価を受けた。
しかし時を経た現在、立憲民主党は公約に「食料品の消費税ゼロ」を掲げた。この方針転換は、単なる経済状況の変化では説明できない。13年前の主張とは真逆な政策を打ち出すのなら、その意図と合理的な理由を示すのが当たり前だ。かつての「増税の責任者」が、一転して減税を唱えるのなら、選挙目当ての公約と受け止められても仕方ない。
「食料品の消費税ゼロ」で一番恩恵を受けるのは、消費額の大きい高所得層だ。高所得層が恩恵を与えるためになぜ、「社会保障を支える責任ある財源」である消費税を減税しなければならないのか。また、ゼロ税率の実施によって数兆円規模の税収減が生じれば、その補填財源をどう確保するかについても決まっていない。
政治家も政党も現在の社会はもちろん、将来の社会に対しても責任を負っている。だからこそ野田代表は首相当時に、少子高齢化が進む社会に向け「消費税は社会保障を支える責任ある財源」と訴えたはずだ。
それが選挙を前にすると、一転して「消費税減税」だ。これでは高所得層は別として、これから将来を切り拓いていく若者たちは浮かばれない。